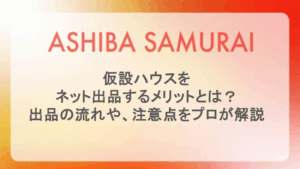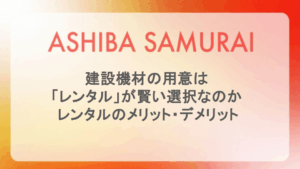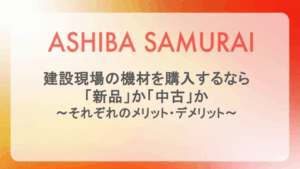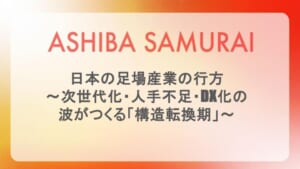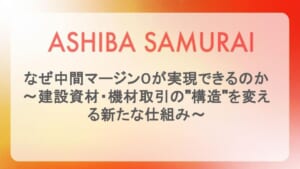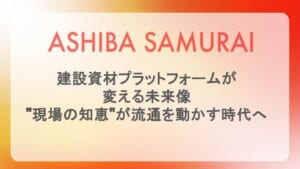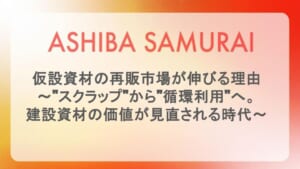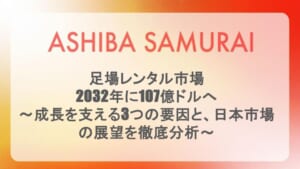「先日、500万円を超える大きな工事の話があったのに、許可がないせいで断らざるを得なかった…」
「事業を拡大したいが、許可の手続きが複雑そうで、どこから手をつけていいか分からない…」
このような悔しい思いや、漠然とした不安を抱えていらっしゃる建設業の経営者様は少なくありません。日々現場や経営に追われる中で、煩雑な手続きは後回しになりがちですよね。
ご安心ください。この記事を最後までお読みいただければ、建設業許可証に関する全ての疑問が解消されます。許可の必要性から、複雑な要件、具体的な申請ステップ、さらには許可取得後の注意点まで、網羅的に解説します。
この記事は、単なる手続きの解説書ではありません。建設業許可証を、事業を次のステージへ進めるための「信頼の証」として活用するための戦略書です。正しい知識を身につけ、未来への扉をスムーズに開きましょう。
(本記事は、令和6年4月時点の法令に基づき、建設業許可を専門とする行政書士の監修のもと作成しています。)
まずはここから!建設業許可証の基礎知識
建設業許可証について深く理解する前に、まずは「なぜ必要なのか」「どんなメリットがあるのか」という基本的な部分をしっかりと押さえましょう。ここを理解することが、面倒な手続きを乗り越えるモチベーションに繋がります。
そもそも建設業許可証とは?事業成長のパスポート
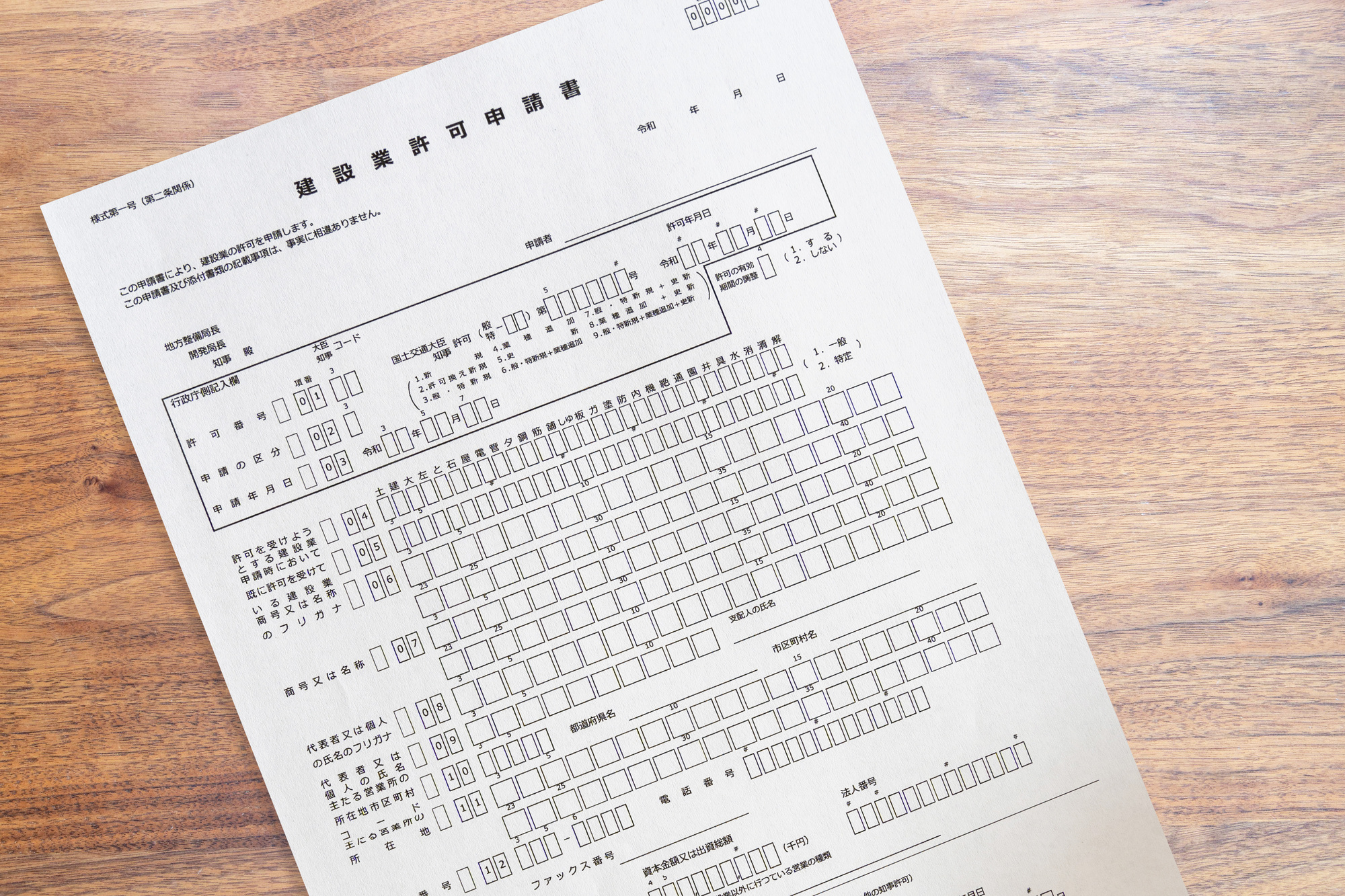
建設業許可証とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な、都道府県知事または国土交通大臣から与えられる公的な許可のことです。これは建設業法という法律で定められており、無許可で大規模な工事を行うと厳しい罰則が科せられます。しかし、この許可証は単なる法的な義務ではありません。企業の技術力や経営基盤が一定水準以上であることを公的に証明する「信頼のパスポート」と考えるべきです。許可取得は、事業の安定と成長を目指す上で不可欠な第一歩なのです。
【5分でわかる】許可が必要な工事と不要な工事の境界線
「うちの会社は本当に許可が必要なのだろうか?」これは多くの経営者様が最初に抱く疑問です。建設業法では、全ての工事に許可が必要なわけではなく、「軽微な建設工事」については許可がなくても請け負うことが認められています。その境界線は、主に工事1件あたりの請負代金の額によって決まります。具体的には以下の通りです。
| 工事の種類 | 許可が不要な工事(軽微な建設工事)の基準 | 許可が必要な工事の例 |
|---|---|---|
| 建築一式工事 | 請負代金が1,500万円未満の工事 または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 | 請負代金1,500万円以上の新築工事 |
| 建築一式工事以外 | 請負代金が500万円未満の工事 | 請負代金500万円以上の内装リフォーム工事 |
ここで注意すべきポイントは、この金額が消費税込みであり、材料費も含まれるという点です。元請から材料が支給される場合でも、その市場価格を含めて計算する必要があるため、この「500万円の壁」を知らずに契約すると法令違反になる可能性があります。
許可取得の3大メリット!信頼と受注機会が飛躍的に向上
建設業許可を取得するメリットは、単に高額な工事が受注できるようになるだけではありません。第一に社会的信用の獲得が挙げられます。許可証は経営体制や技術力が公的に認められた証であり、顧客や取引先、特に金融機関からの信用が大幅に向上します。次に受注機会の拡大も重要なメリットです。500万円以上の工事はもちろん、公共工事の入札参加には許可が必須です。近年は元請の大手企業も下請選定の絶対条件とすることが一般的です。そして最後に、法令遵守(コンプライアンス)の証明にも繋がり、企業のブランドイメージ向上や人材確保にも良い影響を与えます。
あなたの会社はどれ?建設業許可証の種類を完全理解
建設業許可は1種類だけではありません。「事業内容」や「営業所の場所」によって取得すべき許可が異なります。自社がどの許可を目指すべきかをここで明確にしておきましょう。
「一般建設業」と「特定建設業」の違いとは?
建設業許可は、まず「一般建設業」と「特定建設業」の2つに大別されます。この違いは、元請として受注した工事を、どのくらいの規模で下請に出すかによって決まります。
| 項目 | 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
|---|---|---|
| 必要なケース | ・下請として工事を請け負う場合 ・元請だが、下請契約額が4,500万円未満の場合 | ・元請として受注し、合計4,500万円以上の工事を下請に出す場合 ※建築一式工事は7,000万円以上 |
| 取得難易度 | 標準 | 高い(特に財産要件が厳しい) |
| 主な対象者 | 多くの建設業者、専門工事業者 | 大手・中堅のゼネコン、元請中心の工務店 |
発注者から直接請け負う元請業者であっても、下請に出す金額が上記の基準未満であれば「一般建設業許可」で問題ありません。まずはほとんどの事業者が「一般建設業許可」の取得を目指すことになります。将来的に大規模な元請工事を目指す段階で、「特定建設業許可」へのステップアップを検討しましょう。
「知事許可」と「大臣許可」どちらが必要?判断基準を解説
次に、「知事許可」と「大臣許可」の違いを理解しましょう。この区別は事業規模の大小ではなく、建設業を営む営業所の所在地によって決まります。
| 許可の種類 | 必要なケース | 申請先 |
|---|---|---|
| 知事許可 | 1つの都道府県のみに営業所を設置する場合 | 営業所の所在地を管轄する都道府県 |
| 大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合 | 国土交通省(地方整備局など) |
ここで言う「営業所」とは、本店や支店など、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。単なる資材置き場や作業員詰所は該当しません。例えば、本社(東京都)のみで全ての契約を行い、工事現場が他県にあるという場合は「知事許可」で問題ありません。本社が東京、支店が神奈川にあってそれぞれ契約行為を行う場合は「大臣許可」が必要になります。
29種類の専門工事|あなたの業種はどれに当てはまる?
建設業許可は、さらに29の専門工事(業種)に分かれています。自社が行う工事内容に応じて、必要な業種の許可を取得する必要があります。大きく分けると、土木一式と建築一式の「一式工事(2業種)」と、より専門的な「専門工事(27業種)」です。例えば、大工工事や内装仕上工事、とび・土工・コンクリート工事、電気工事、管工事などがあります。自社の主力事業がどの業種に該当するかを正確に把握し、複数の業種の工事を請け負う場合は、それぞれの業種で許可を取得する必要があります。どの業種で申請すべきか迷った際は、行政の担当窓口や専門家に相談しましょう。
【最重要】許可取得の5大要件を徹底解説
ここが建設業許可取得における最大の関門です。法律で定められた5つの要件をすべてクリアする必要があります。一つずつ、分かりやすく解説していきます。
要件1:経営業務の管理責任者(経管)を置くこと

建設業の経営は専門性が高いため、許可を受ける会社には「経営経験が豊富な人物」を役員として配置することが求められます。この人物を「経営業務の管理責任者(経管)」と呼びます。経管になるには、許可を受けたい業種で法人の役員または個人事業主として5年以上、あるいはそれ以外の建設業種で6年以上の経営経験が必要です。この「経営経験」は、過去の確定申告書や工事の契約書などで客観的に証明する必要があり、許可申請における重要なポイントとなります。
要件2:専任技術者(専技)を営業所に置くこと

各営業所には、工事に関する専門的な知識や経験を持つ「専任の技術者」を配置しなければなりません。これを「専任技術者(専技)」と呼びます。専技になるには複数のルートがあり、最も証明しやすいのは取得したい業種に関連する国家資格(例:1級建築士など)を保有しているケースです。資格がない場合でも、指定学科の高校を卒業後5年以上、または大学卒業後3年以上の実務経験や、学歴に関わらず10年以上の実務経験があることで要件を満たせます。この実務経験も、過去の工事契約書などで証明が必要です。
要件3:財産的基礎・金銭的信用(500万円の壁)
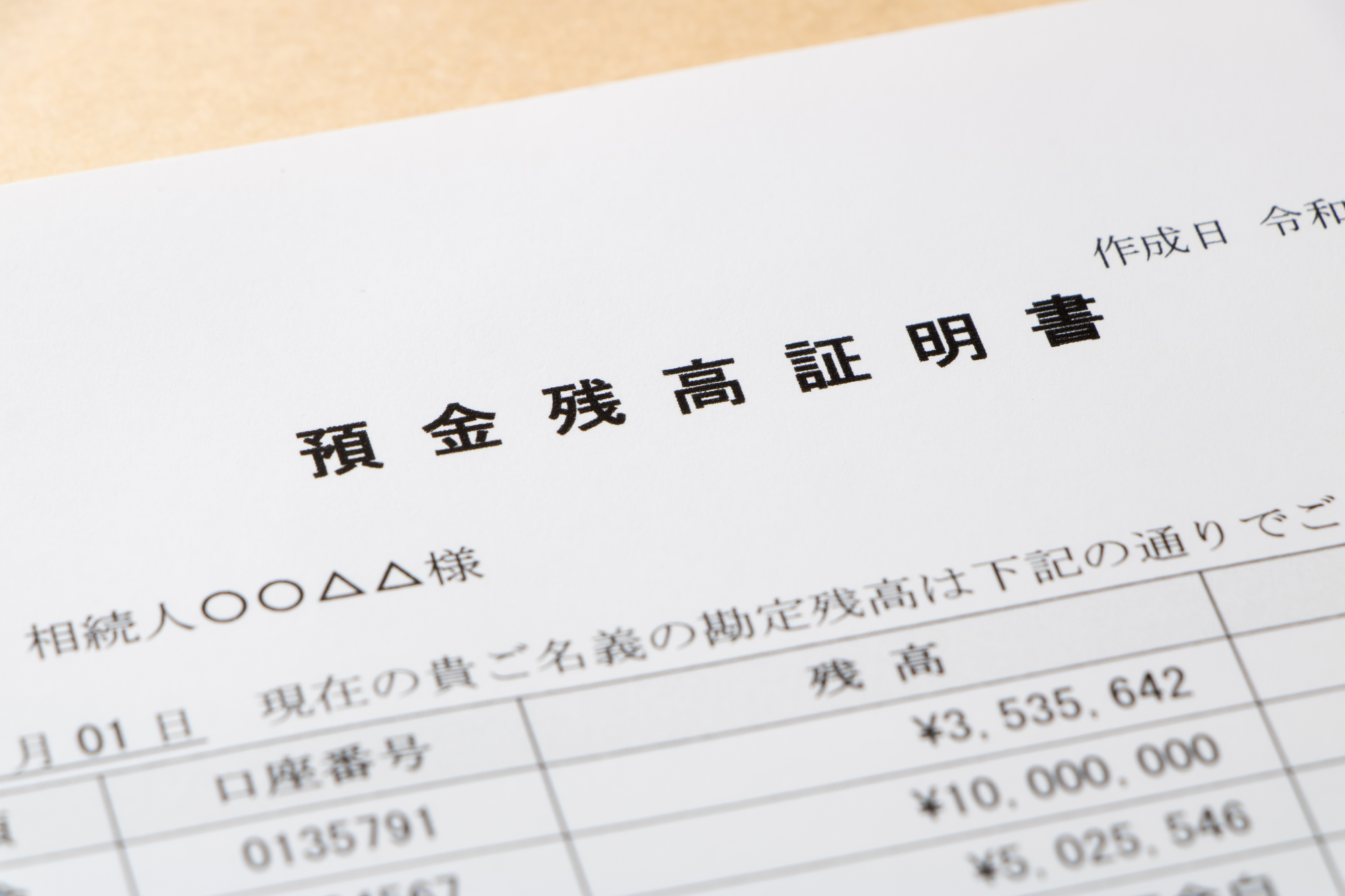
建設工事は多額の資金が必要になるため、許可を受ける会社には安定した経営基盤が求められます。これを「財産的基礎」の要件と呼びます。一般建設業許可の場合、直前の決算書において自己資本の額が500万円以上であるか、または500万円以上の資金調達能力があることのいずれかを満たす必要があります。決算書で自己資本が500万円に満たない場合でも、金融機関が発行する「500万円以上の預金残高証明書」を提出することで、この要件をクリアすることが可能です。
要件4:誠実性の要件

これは、許可を申請する法人やその役員、個人事業主などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことを求める要件です。具体的には、過去に建築士法や宅地建物取引業法などで不正な行為により免許を取り消されたり、業務停止処分を受けたりしていないかが審査されます。暴力団の構成員である場合なども、この要件を満たさないと判断されます。通常の事業を真面目に行っている限り、この要件で問題になることはほとんどありません。
要件5:欠格要件に該当しないこと
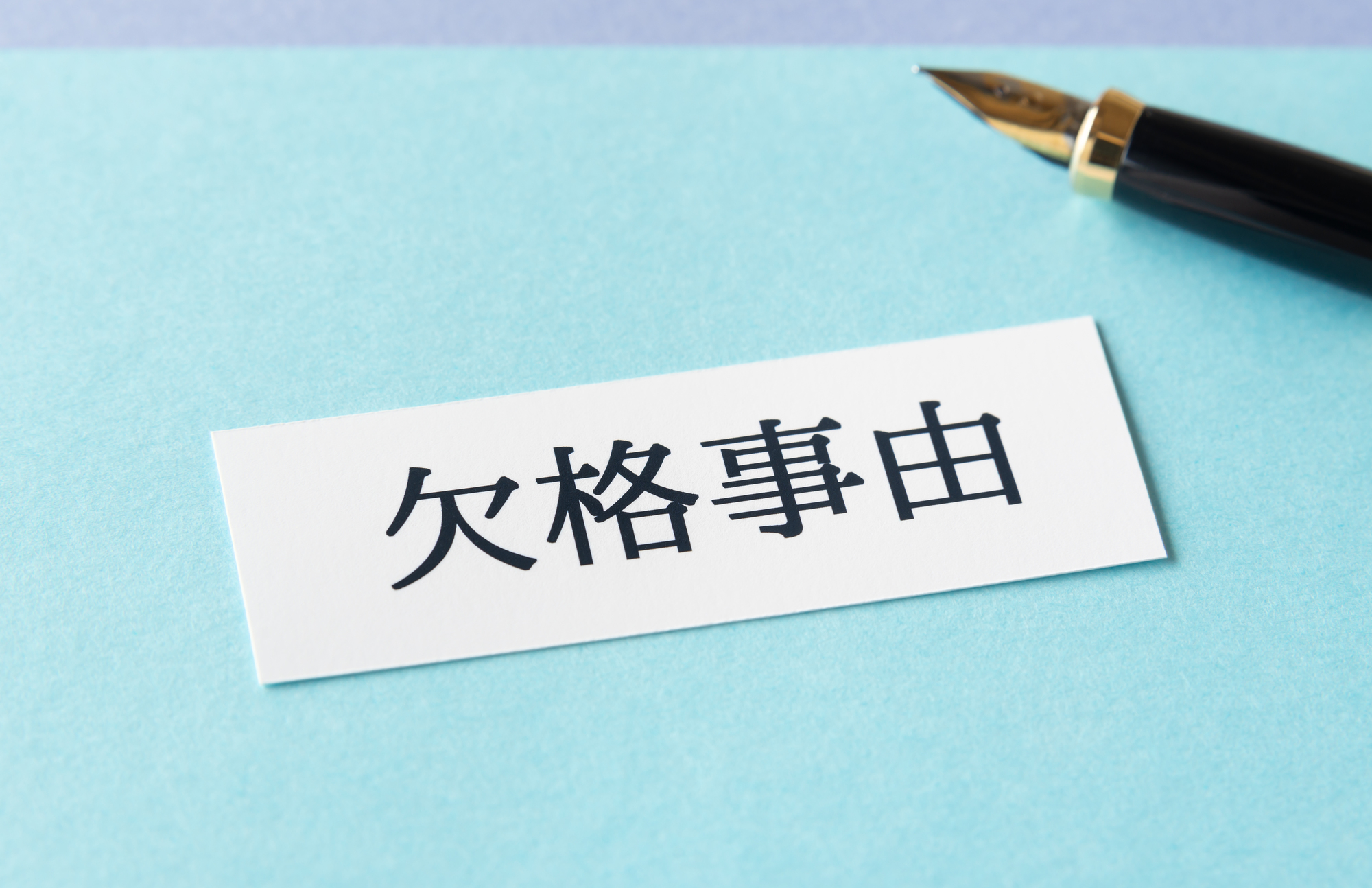
最後に、申請者や役員が、法律で定められた「欠格要件」に該当しないことが必要です。これには、過去に建設業許可を取り消されてから5年が経過していない、禁錮以上の刑に処せられてから5年が経過していないといった項目が含まれます。誠実性の要件と同様、法令を遵守して事業を行っていれば、通常は該当することはありません。申請前に役員の中に該当者がいないかを確認しておくことが大切です。
【実践ツール】ウチは要件を満たしてる?許可取得セルフチェックリスト
ここまでの5大要件を、ご自身の会社に当てはめてチェックしてみましょう。
| 要件 | チェック項目 | はい/いいえ |
|---|---|---|
| 1. 経営業務の管理責任者 | 役員の中に、5年以上の建設業経営経験を持つ人はいますか? | |
| 2. 専任技術者 | 営業所に常勤で、国家資格者または10年以上の実務経験者はいますか? | |
| 3. 財産的基礎 | 直前の決算書で、自己資本が500万円以上ありますか? (上記が「いいえ」の場合)500万円以上の預金残高証明書は用意できますか? | |
| 4. 誠実性 | 契約に関して、過去に不正や不誠実な行為はありませんか? | |
| 5. 欠格要件 | 役員の中に、法律で定められた欠格要件に該当する人はいませんか? |
このリストで全て「はい」となれば、許可取得の可能性は非常に高いと言えます。もし「いいえ」の項目があれば、その部分をどうクリアするかを重点的に検討する必要があります。
もう迷わない!申請手続きの完全ステップガイド
要件をクリアできる見込みが立ったら、次はいよいよ申請手続きです。複雑に見えますが、一つ一つのステップを順番に進めていけば、必ずゴールにたどり着けます。
ステップ1:事前準備と必要書類の収集

申請手続きで最も時間と労力がかかるのが、この必要書類の収集です。申請先の都道府県によって様式や求められる書類が若干異なりますが、建設業許可申請書をはじめ、役員の身分証明書や登記されていないことの証明書、各種要件を証明するための書類など多岐にわたります。特に、経営経験や実務経験を証明するための過去の工事契約書や注文書は、数年分遡って探し出す必要があるため、早めに準備を始めることが成功の鍵です。
【具体例】特に注意が必要な書類一覧
膨大な書類の中でも、特に準備に時間がかかり、注意が必要なものをピックアップして解説します。
| 書類名 | 取得場所・作成者 | 注意点 |
|---|---|---|
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村役場 | 運転免許証等ではなく、破産者でないことを証明する公的書類です。 |
| 登記されていないことの証明書 | 法務局 | 成年被後見人・被保佐人でないことを証明する書類です。郵送も可能です。 |
| 工事経歴書 | 申請者が作成 | 申請する業種について、主要な工事の実績を具体的に記載します。 |
| 工事請負契約書等 | 自社で保管 | 経管や専技の経験証明に5〜10年分が必要なことも。紛失時は代替資料の相談が必要です。 |
これらの書類は、一つでも不備があると申請が受理されなかったり、審査が長引いたりする原因になります。リストを作成し、一つずつ着実に揃えていきましょう。
ステップ2:申請書の作成と提出

必要書類がすべて揃ったら、申請書を作成します。各都道府県のウェブサイトから様式をダウンロードし、手引きを見ながら記入していきます。記載内容に誤りがないか、添付書類と矛盾がないかを何度も確認しましょう。全ての書類が完成したら、管轄の土木事務所などの行政窓口へ提出します。提出時には、担当者から内容について質問されることもあるため、申請内容をしっかりと説明できるようにしておくことが望ましいです。申請が受理されると、法定手数料を納付し、審査開始を待ちます。
ステップ3:審査期間と許可証の交付

申請が受理されてから許可が下りるまでの標準的な審査期間は、知事許可で約30日~60日、大臣許可では約90日~120日が目安です。この期間は、申請先の行政庁や申請内容によって変動します。審査期間中は、行政から内容の確認や追加資料の提出を求められることもありますので、提出した書類の控えは必ず保管しておきましょう。無事に審査が完了すると「許可通知書」が郵送で届きます。これで晴れて建設業許可業者となり、500万円以上の工事を請け負うことができるようになります。
費用は?誰に頼む?専門家(行政書士)選びのポイント
許可取得には、当然ながら費用がかかります。また、「本当に自分でできるのか?」と不安に思う方も多いでしょう。ここでは、費用と専門家の活用について解説します。
許可取得にかかる費用の全貌
建設業許可の取得にかかる費用は、大きく分けて「法定手数料」と「専門家への報酬」の2つです。
| 費用項目 | 金額の目安 | 支払い先 |
|---|---|---|
| 法定手数料 | 知事許可:9万円 大臣許可:15万円 | 都道府県や国 |
| 専門家(行政書士)への報酬 | 10万円~20万円程度 | 行政書士事務所 |
法定手数料は、許可の審査をしてもらうために必ず支払う公的な費用です。これに加えて、行政書士に手続きを依頼する場合は、その代行手数料(報酬)が発生します。報酬額は事務所によって異なりますが、書類収集から申請代理まで一式で10万円~20万円程度が相場です。その他、証明書類の取得にかかる実費も別途必要となります。
自分で申請 vs 行政書士に依頼|メリット・デメリットを比較
費用を抑えるために自分で申請するか、専門家である行政書士に依頼するかは非常に悩ましい問題です。それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。
| 自分で申請する | 行政書士に依頼する | |
|---|---|---|
| メリット | ・費用を抑えられる(法定手数料のみ) ・手続きの知識が身につく | ・時間と手間を大幅に削減できる ・許可取得の確実性が高い ・複雑な要件の判断を任せられる |
| デメリット | ・膨大な時間と手間がかかる ・書類の不備で何度もやり直しになるリスク ・要件の解釈を誤り、不許可になる可能性 | ・報酬費用がかかる |
多忙な経営者様にとって、時間は最も貴重な経営資源です。不慣れな書類作成や役所とのやり取りに時間を費やすよりも、その時間を本業に充てた方が、結果的に会社にとってプラスになるケースも少なくありません。自社の状況に合わせて最適な方法を選択することが重要です。
失敗しない行政書士選びの3つのコツ
もし行政書士に依頼すると決めた場合、信頼できるパートナーを選ぶことが重要です。まず第一に、建設業許可の専門性が高い事務所を選びましょう。ウェブサイトなどで実績を確認するのがおすすめです。次に、料金体系が明確であることも大切です。どこまでの業務が含まれるのか、追加料金の有無などを事前に確認しましょう。最後に、コミュニケーションの取りやすさも無視できません。専門用語を分かりやすく説明してくれるかなど、担当者との相性も重要です。許可取得後も長い付き合いになる可能性があるため、気軽に相談できる相手が理想です。
許可取得後も安心!維持に必要な重要手続き
建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。許可を維持するためには、定期的に行うべき重要な手続きがあります。これらを怠ると、最悪の場合、許可が取り消されてしまうこともあるため、必ず覚えておきましょう。
毎年必須!事業年度終了報告書(決算変更届)
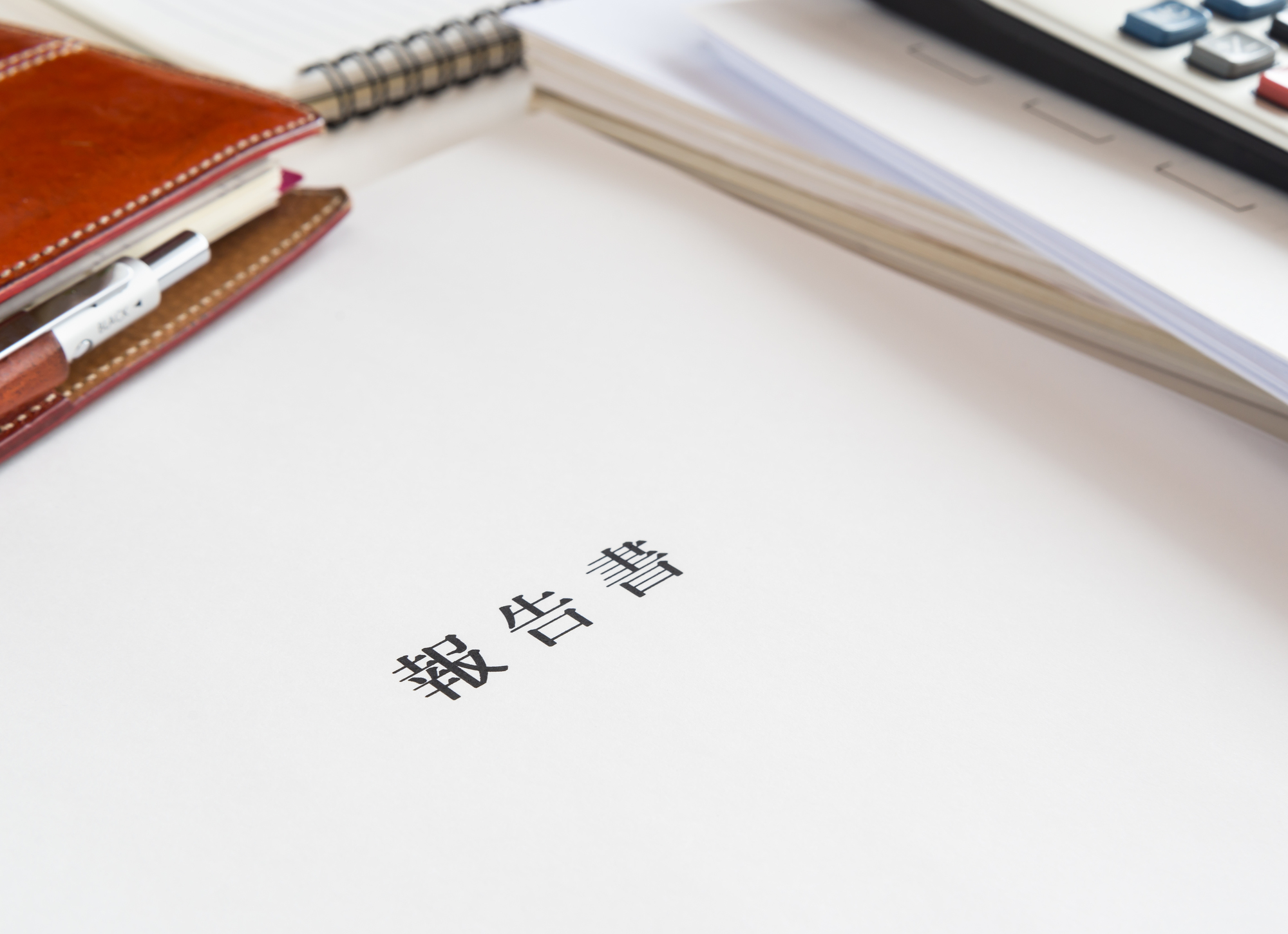
建設業許可業者は、事業年度が終了してから4ヶ月以内に、その事業年度の工事実績や財務状況をまとめた「事業年度終了報告書(決算変更届)」を提出する義務があります。これは、許可行政庁が「この会社は許可基準を維持できているか」を毎年チェックするための重要な手続きです。この届出を怠ると、後述する更新手続きが受け付けてもらえません。税務申告が終わったら、忘れずに建設業の決算変更届も行うサイクルを社内で確立しましょう。
5年に一度の更新手続きを忘れると大変なことに

建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き許可を維持するためには、有効期間が満了する日の30日前までに更新の申請を行う必要があります。もしこの更新手続きを忘れてしまうと、許可は失効してしまいます。再び許可を取得するには、また一から新規申請の手続きと費用が必要となり、その間は500万円以上の工事を請け負えません。事業への影響は計り知れないため、許可証の有効期間満了日は必ず管理し、余裕を持ったスケジュールで準備を進めましょう。
会社情報に変更があった場合の各種変更届
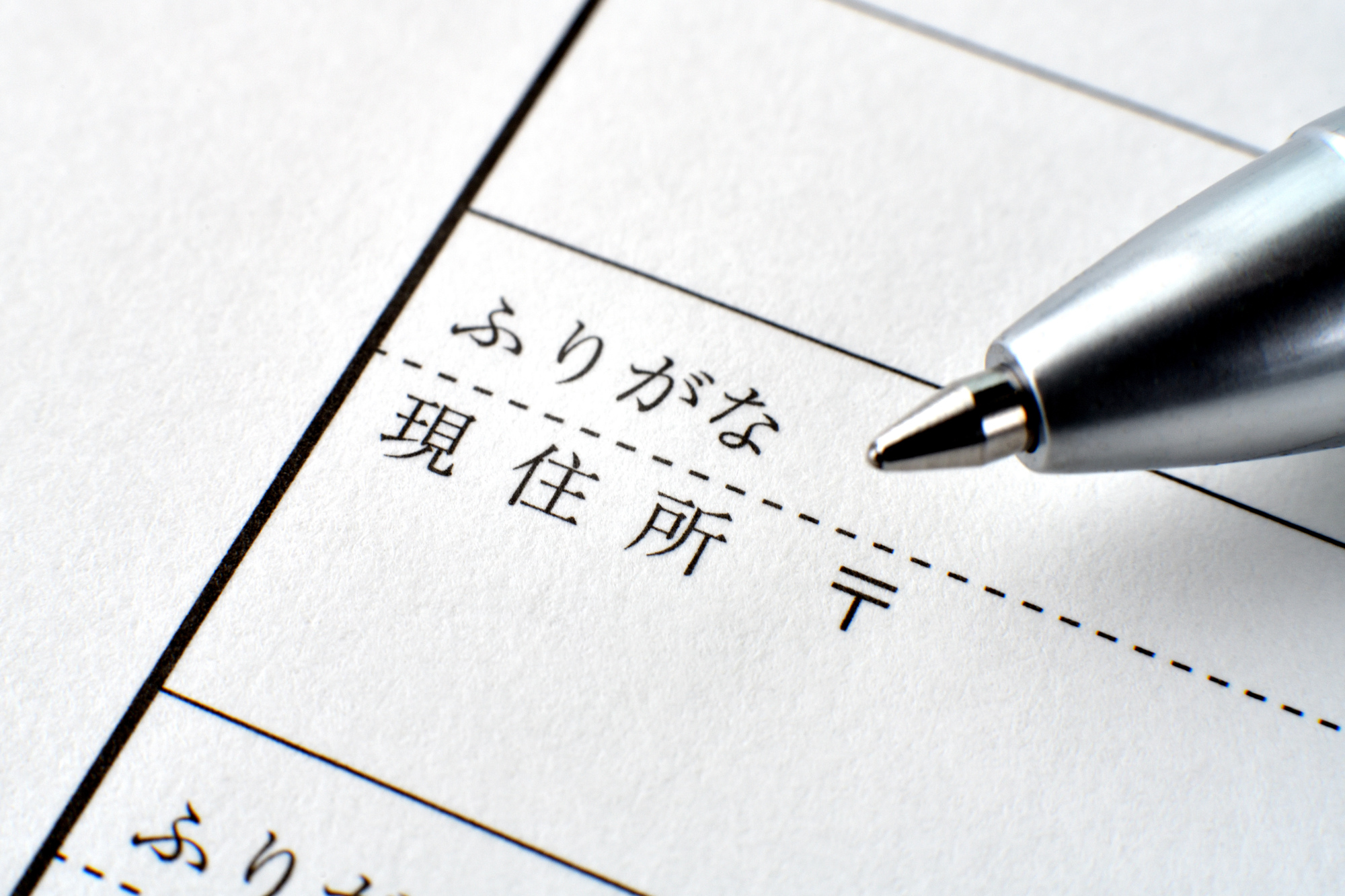
許可を取得した後に、会社の内容に変更が生じた場合は、その都度、変更届を提出する必要があります。例えば、商号や所在地の変更、役員の就任・退任、経営業務の管理責任者や専任技術者の交代などが該当します。これらの変更届は、変更があった日から定められた期間内(2週間または30日以内)に提出しなければなりません。特に、経営や技術の要である経管や専技の変更は許可の根幹に関わるため、後任者の要件などを事前に専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ:建設業許可証は未来への投資
今回は、建設業許可証の基礎知識から種類、最重要である5つの要件、具体的な申請ステップ、そして取得後の注意点まで網羅的に解説しました。複雑に見える手続きも、一つずつ分解して理解すれば、決して乗り越えられない壁ではありません。建設業許可証は、単なる法的な義務ではなく、会社の信用を高め、事業の可能性を大きく広げるための「未来への投資」です。許可取得によって、これまで諦めていた大規模工事の受注や公共工事への参入といった、新しいステージへの道が拓けます。この記事が、皆様の事業のさらなる発展の一助となれば幸いです。