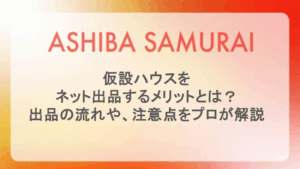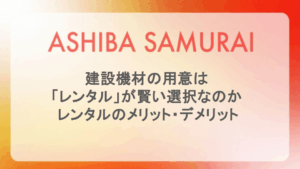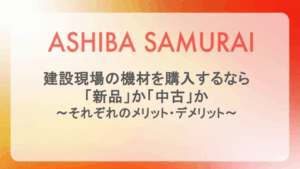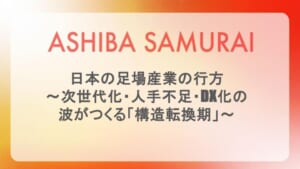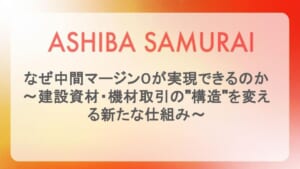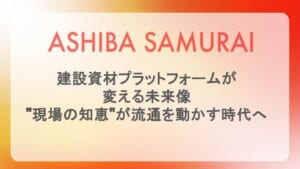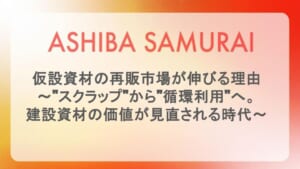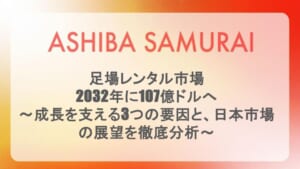「長年使い慣れたExcelでの積算も、そろそろ限界かもしれない…」
「積算ミスによる手戻りや赤字案件を防ぎたいが、若手に教える時間もない…」
中小建設会社で積算業務を担う担当者様の中には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。人手不足が深刻化し、建設DXが叫ばれる昨今、従来の積算業務の在り方は大きな転換期を迎えています。
この記事では、建設業界の専門家の監修のもと、数ある建設業向け積算ソフトの中から、自社の課題や規模に最適な一社を見つけるための実践的な選び方を徹底解説します。
さらに、目的別のおすすめソフト比較や、実際に導入した企業の成功事例もご紹介します。この記事を読み終える頃には、あなたは自社に合ったソフトの候補を具体的に絞り込み、自信を持って導入を提案できるようになっているはずです。
なぜ今、建設業で積算ソフトが必要なのか?Excel管理の限界とDXの重要性
長年、建設業界の積算業務を支えてきたExcelですが、その利便性の裏側で多くの課題が潜んでいます。なぜ今、多くの企業がExcelから専用の積算ソフトへ移行しているのでしょうか。そこには、無視できない3つの限界と、企業としての成長戦略が関わっています。
手作業による積算ミスの頻発と利益損失のリスク
Excelによる積算業務は、手入力や数式のコピー&ペーストが基本となるため、ヒューマンエラーが起こりやすいという構造的な問題を抱えています。例えば、歩掛の数値を一桁間違える、拾い出した数量の転記を忘れるといった単純なミスが、最終的な見積金額に大きな影響を与え、赤字案件に直結することも少なくありません。このようなミスは企業の利益を直接圧迫するだけでなく、顧客からの信頼を失う原因にもなり得ます。専用の積算ソフトは、単価マスタや歩掛データと連携し、計算を自動化することで、これらのリスクを大幅に軽減します。
業務の属人化と技術継承の課題
「この積算は、ベテランの○○さんしかできない」という状況は、多くの中小建設会社が抱える深刻な課題です。Excelの複雑な計算式や独自の管理方法は、担当者個人の知識と経験に大きく依存するため、業務の属人化を招きます。この状態では、担当者の急な退職や異動があった際に業務が滞ってしまうリスクがあります。また、若手社員に積算業務を教える時間がない中で、標準化されていないExcelファイルを渡しても、技術の継承は困難です。積算ソフトを導入することは、業務フローを標準化し、誰が担当しても一定の品質を担保できる体制を築くための第一歩となります。
法改正や資材価格の変動にスピーディに対応できない
建設業界は、働き方改革関連法やインボイス制度といった法改正、そしてウッドショックに代表されるような急激な資材価格の変動に常に晒されています。Excelでこれら最新の情報を正確に、かつ迅速に見積もりに反映させるのは至難の業です。単価マスタを手作業で一つひとつ更新するには膨大な時間がかかり、対応の遅れは見積もりの精度低下に繋がります。多くの積算ソフトは、最新の公共工事設計労務単価や資材価格データを定期的に配信・更新する機能を備えており、常に正確な情報に基づいた積算を可能にします。
失敗しない建設業向け積算ソフトの選び方|5つの重要比較ポイント
積算ソフトの導入は、決して安くない投資です。「導入したものの、使いこなせなかった」という事態を避けるためにも、自社の状況に合ったソフトを慎重に選ぶ必要があります。ここでは、選定時に必ず確認すべき5つの重要な比較ポイントを解説します。
ポイント1:企業の規模と専門分野(建築・土木・設備)に合っているか
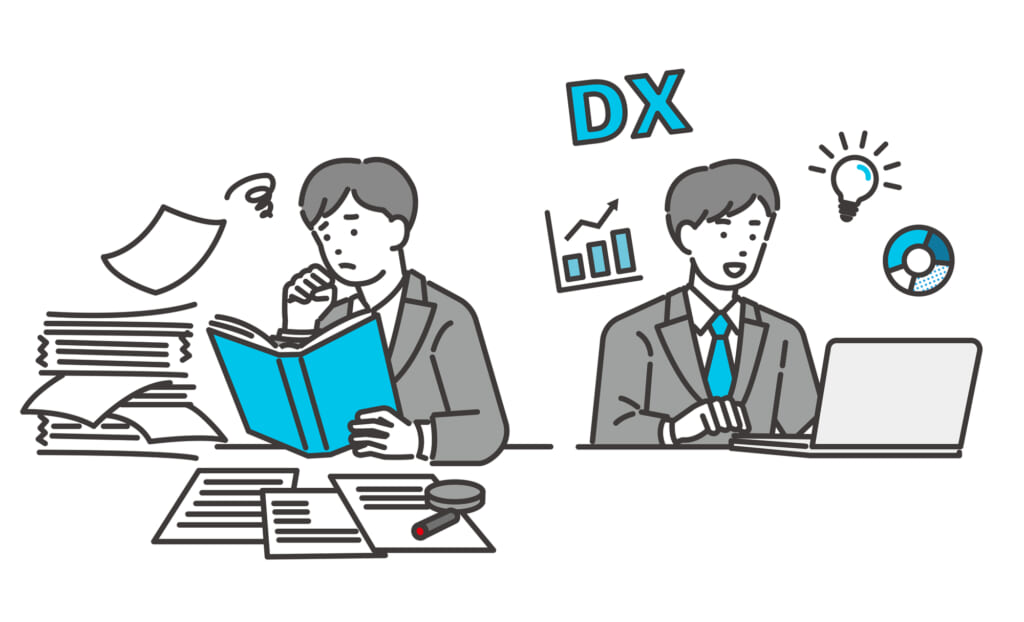
積算ソフトは、対応する企業の規模や専門工事によって機能が大きく異なります。従業員数が数十名規模の中小企業であれば、操作がシンプルでコストを抑えたソフトが適しているでしょう。一方で、大規模なプロジェクトを扱うゼネコンでは、詳細な原価管理や複数の担当者でデータを共有できる高機能なソフトが求められます。また、建築、土木、電気設備、空調衛生設備など、自社の専門分野に特化した機能を搭載しているかも重要な選定基準です。特化型ソフトは、その分野で頻繁に使用する部材や歩掛があらかじめ登録されており、積算業務を大幅に効率化できます。
ポイント2:ソフトの提供形態(クラウド型 vs インストール型)
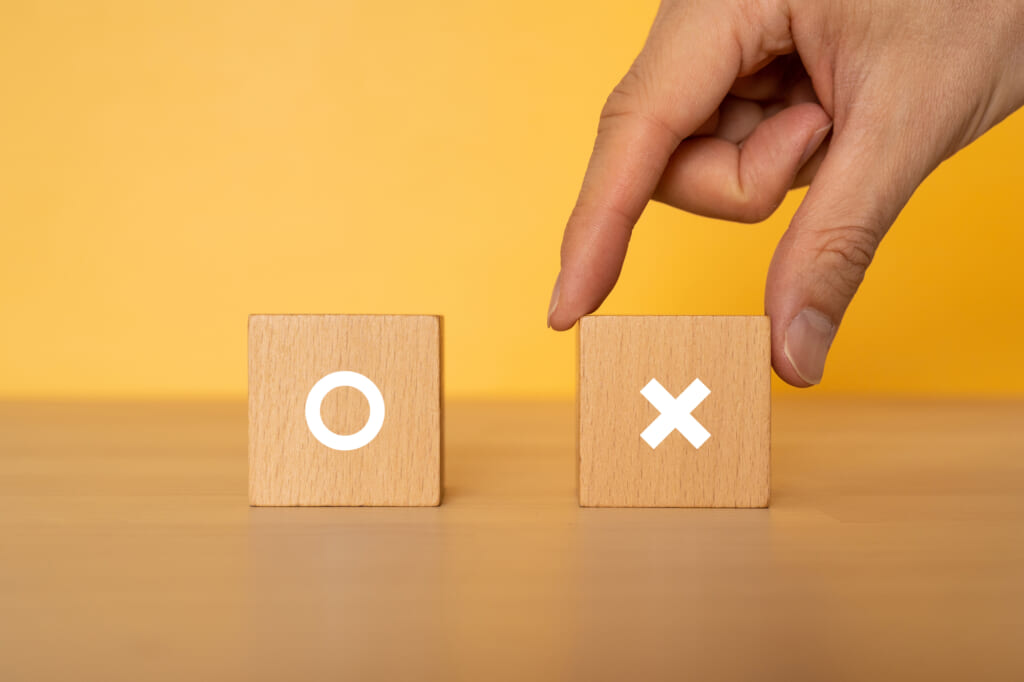
積算ソフトには、主に「クラウド型」と「インストール型」の2種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の働き方やIT環境に合わせて選びましょう。特に近年は、現場や自宅など場所を選ばずに利用できるクラウド型が主流になりつつあります。
| 提供形態 | メリット | デメリット | こんな企業におすすめ |
|---|---|---|---|
| クラウド型 | ・インターネット環境があればどこでも利用可能 ・複数人でのリアルタイムな情報共有が容易 ・法改正や単価改定時に自動でアップデート ・初期費用が安価な場合が多い | ・月額/年額のランニングコストが発生 ・インターネット環境がないと利用できない ・カスタマイズの自由度が低い場合がある | ・テレワークや現場での利用が多い ・複数拠点でデータを共有したい ・初期費用を抑えたい |
| インストール型 | ・オフラインでも利用可能 ・買い切り型が多く、ランニングコストを抑えられる ・動作が安定しており、処理速度が速い ・カスタマイズ性が高い製品が多い | ・特定のPCでしか利用できない ・初期費用が高額になる傾向がある ・アップデートやデータ管理を自社で行う必要がある | ・特定の事務所内での利用が中心 ・長期的なコストを抑えたい ・セキュリティ要件が厳しい |
ポイント3:操作性の高さとサポート体制の手厚さ
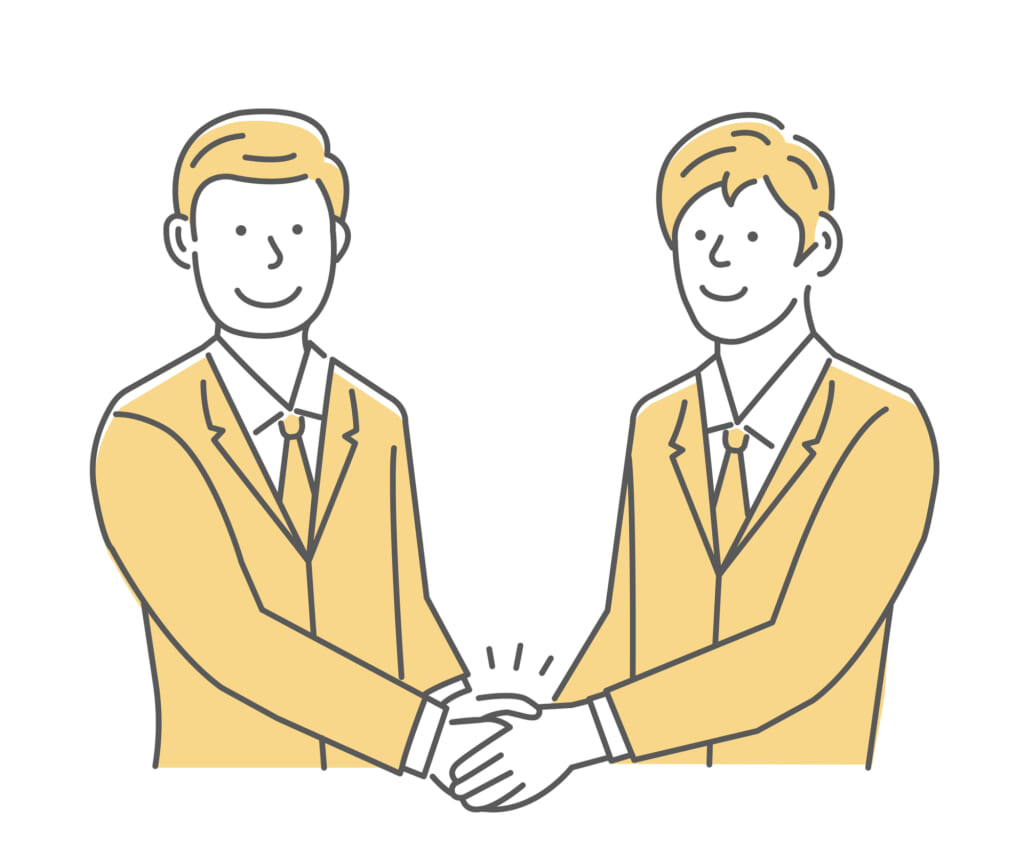
どんなに高機能なソフトでも、操作が複雑で使いこなせなければ意味がありません。特に、パソコン操作に不慣れな従業員がいる場合は、Excelのように直感的に扱えるインターフェースかどうかが重要になります。多くのソフトメーカーが無料トライアルやオンラインデモを提供しているため、必ず事前に操作性を確認しましょう。また、導入後のサポート体制も非常に重要です。導入時の初期設定支援、電話やメールでの問い合わせ対応、オンラインでの操作研修など、サポートが手厚いメーカーを選ぶことで、導入後のつまずきを最小限に抑え、社内への定着をスムーズに進めることができます。
ポイント4:費用対効果(価格体系とランニングコスト)
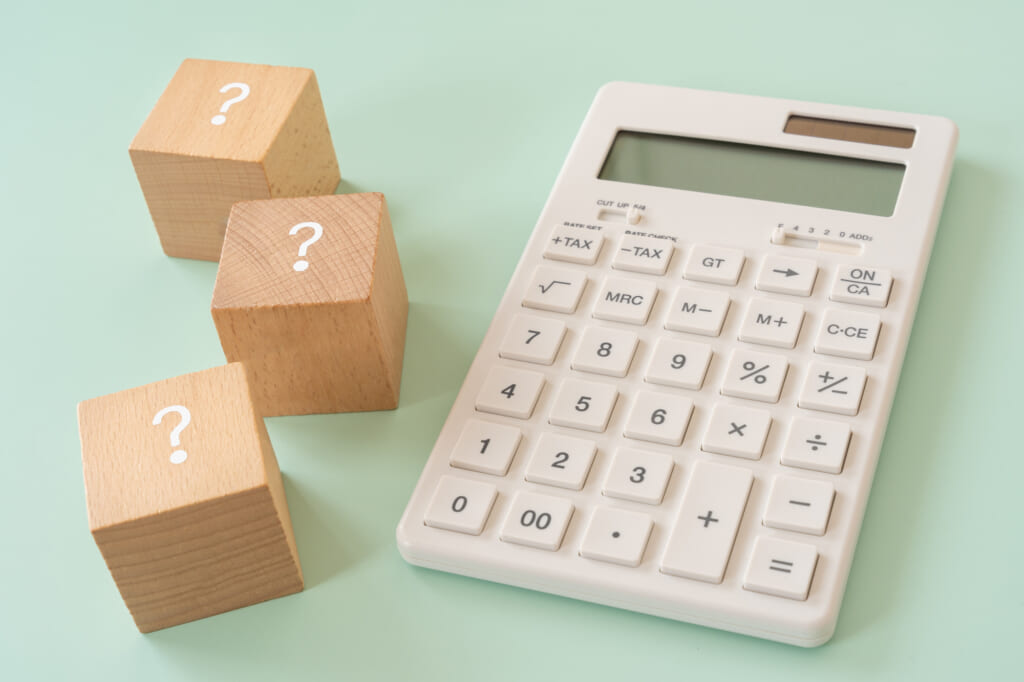
積算ソフトの価格体系は、初期費用と月額費用がかかるサブスクリプション型と、最初に一括で支払う買い切り型に大別されます。価格だけを見て判断するのではなく、導入によって得られる効果を総合的に考える「費用対効果」の視点が不可欠です。例えば、月額3万円のソフトを導入することで、積算担当者の残業代が月5万円削減され、さらに積算ミスによる損失が年間数十万円防げるとしたら、それは十分に価値のある投資と言えるでしょう。自社の予算と、ソフト導入によって解決したい課題の大きさを天秤にかけ、長期的な視点で判断することが重要です。
ポイント5:他システムとの連携性(BIM/CIM、会計ソフトなど)
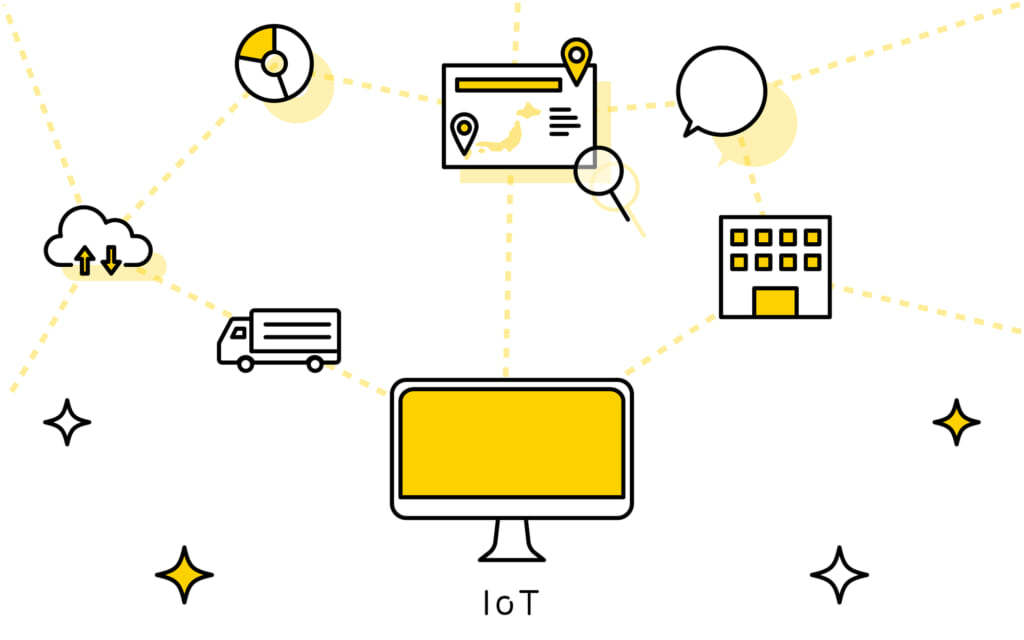
建設DXを推進していく上では、積算ソフトが他のシステムとどれだけスムーズに連携できるかも重要なポイントです。近年注目されているBIM/CIMと連携できれば、3Dモデルから自動で数量を拾い出し、積算業務を劇的に効率化できます。また、会計ソフトと連携して見積データを請求書に反映させたり、工程管理ソフトと連携して実行予算を管理したりすることで、業務全体の生産性が向上します。将来的な事業拡大や業務効率化の可能性を見据え、拡張性の高いソフトを選んでおくと良いでしょう。
【目的別】建設業積算ソフトおすすめ15選を徹底比較
ここからは、前述した5つの選び方を踏まえ、具体的な積算ソフトを「中小企業向け」「専門工事特化型」「多機能・BIM連携」の3つの目的別に分けてご紹介します。自社のニーズに最も近いカテゴリーからご覧ください。
(ここでは代表的なソフトの例をいくつか挙げます。実際の記事では、より多くのソフトウェアを詳細な比較表と共に紹介します。)
【中小企業向け】コストと機能のバランスが良いおすすめソフト5選
初めて積算ソフトを導入する中小企業や、コストを抑えつつ業務効率化を実現したい企業におすすめのソフトです。操作の分かりやすさと、導入しやすい価格帯が魅力です。
楽王シリーズ(アークシステム株式会社)

Excelライクな操作性が特徴で、これまでExcelで積算を行っていた方でもスムーズに移行しやすいソフトです。見積書の作成はもちろん、実行予算や原価管理までカバーできる拡張性も備えています。手厚いサポート体制にも定評があり、導入後も安心して利用できる点が多くの企業から支持されています。中小企業が必要とする機能をバランス良く搭載しており、コストパフォーマンスに優れた選択肢と言えるでしょう。
AnyONE(エニワン株式会社)

積算・見積もり機能だけでなく、顧客管理、工程管理、受発注管理、入出金管理など、工務店やリフォーム会社の基幹業務を一元管理できるオールインワンシステムです。複数のソフトを使い分ける必要がなく、情報が一元化されるため、業務全体の効率が格段に向上します。特に、積算から請求までの一連の流れをスムーズにしたいと考えている企業に最適です。
【専門工事特化型】建築・土木・設備別おすすめソフト3選
特定の工事分野に特化した機能を持ち、専門性の高い積算業務を強力にサポートするソフトです。各分野の専門用語や特殊な計算にも対応しています。
ATLUS REAL(株式会社コンピュータシステム研究所)

土木工事積算システムとして、業界内で高いシェアを誇ります。国土交通省や各自治体の最新の積算基準に完全準拠しており、公共工事の積算において絶大な信頼性を誇ります。複雑な土木工事の数量計算を自動化する機能や、電子納品に対応したデータ作成機能も充実しており、土木工事を主軸とする企業にとっては欠かせないツールです。
CADEWA(株式会社四電工)

電気設備・空調衛生設備工事に特化した建築設備CADソフトです。CADで作図した図面から、配線や配管の長さを自動で拾い出し、そのまま見積書を作成できる「図面連動積算」が最大の強みです。図面と見積もりが完全に連動するため、設計変更にも迅速に対応でき、拾い漏れなどのミスを根本から防ぐことができます。設備工事の積算精度とスピードを飛躍的に向上させたい企業におすすめです。
【多機能・BIM連携】DXを加速させる高機能おすすめソフト3選
大規模プロジェクトや、BIM/CIMを活用した先進的な取り組みを行う企業向けのハイエンドなソフトです。詳細な原価分析や経営判断にも活用できます。
HEΛIOΣ(ヘリオス)(株式会社シー・エス・イー)

https://it.kensetsu-plaza.com/cad/pickup/archi/16_healios
大手ゼネコンをはじめ、多くの建設会社で導入実績のある建築積算システムです。RC造からS造、木造まで、あらゆる構造・工法の積算に対応できる柔軟性が特徴です。特にBIM連携機能に優れており、各種BIMソフトから出力されたモデルデータを活用して、高精度な数量算出を自動で行うことができます。企業の積算ノウハウをデータベース化し、全社で共有・活用する仕組みを構築したい企業に最適です。
【独自取材】積算ソフト導入の成功事例インタビュー
理論や機能比較だけでは分からない、導入後のリアルな声をお届けします。今回は、実際に積算ソフトを導入し、業務改善に成功した2社の担当者様にお話を伺いました。
事例1:株式会社A建設(従業員25名・建築工事)「Excel地獄から解放!残業時間30%削減と若手育成を実現」
導入前の課題:
「以前は、ベテラン社員が作成したExcelの積算シートを使い回していました。しかし、ファイルが複雑化しすぎて、作成者本人しか分からない『ブラックボックス』状態に。些細な修正にも時間がかかり、積算業務だけで毎日2〜3時間の残業が当たり前でした。若手に業務を引き継ごうにも、教える時間もなければ、教えられる標準的な手順もありませんでした。」
選定理由と導入後の成果:
「複数のソフトを比較検討した結果、操作画面が直感的で、電話サポートが充実している現在のソフトに決めました。導入後は、積算業務にかかる時間が平均で30%も削減され、ほぼ定時で帰れるようになりました。空いた時間で現場の確認や若手の指導にあたれるようになり、会社全体の生産性が向上。何より、積算のルールが標準化されたことで、入社2年目の若手社員も自信を持って見積書を作成できるようになったのが最大の成果です。」
積算ソフト導入前に知っておきたい注意点とQ&A
積算ソフトの導入を成功させるためには、事前の準備と正しい知識が不可欠です。導入後に後悔しないために、注意点とよくある質問を確認しておきましょう。
注意点1:データ移行と社内教育の計画を立てる
新しいソフトを導入する際、過去のExcelデータや顧客情報をどう移行するかは重要な課題です。多くのソフトにはデータインポート機能がありますが、事前にデータの整理が必要になる場合もあります。メーカーの担当者と相談し、スムーズなデータ移行計画を立てましょう。また、ソフトは導入して終わりではありません。社内での操作研修会を実施したり、運用ルールを明確に定めたりすることで、全社員がソフトを使いこなし、導入効果を最大限に引き出すことができます。
注意-点2:無料トライアルやデモを必ず活用する
カタログやウェブサイトの情報だけでは、実際の操作感や自社の業務フローに合うかどうかは判断できません。ほとんどのメーカーが無料トライアル期間や、担当者によるオンラインデモを提供しています。これらを積極的に活用し、実際に自社の案件に近い形で見積もりを作成してみることを強くおすすめします。その過程で出てきた疑問点をサポートデスクに問い合わせてみることで、サポートの対応品質を事前に確認することもできます。
よくある質問(FAQ)
Q1. パソコンが苦手な社員でも使えますか?
A. はい、多くの積算ソフトは、Excelに近い感覚で直感的に操作できるよう設計されています。特に中小企業向けのソフトは、ITに不慣れな方でも使いやすいようにシンプルなインターフェースを採用していることが多いです。無料トライアルで実際に触れてみて、操作性を確認することをおすすめします。
Q2. 導入までにかかる期間はどれくらいですか?
A. 企業の規模や導入するソフトによって異なりますが、一般的には問い合わせからヒアリング、契約、導入、初期研修まで含めて1ヶ月〜3ヶ月程度が目安となります。スムーズに進めるためにも、社内で導入目的や解決したい課題を明確にしておくことが重要です。
まとめ:最適な積算ソフトは会社の未来を創る戦略的投資
本記事では、建設業における積算ソフトの必要性から、失敗しない選び方の5つのポイント、そして目的別のおすすめソフトまでを網羅的に解説しました。Excelでの積算業務には限界があり、積算ソフトの導入は、もはや単なるコストではなく、会社の生産性を向上させ、利益を最大化するための「戦略的投資」です。
重要なのは、機能や価格の比較だけで終わらせず、自社の課題を真に解決し、今後の成長を共に歩んでくれる「パートナー」としてのソフトを選ぶことです。まずはこの記事を参考に、自社の課題を整理し、気になるソフトの資料請求や無料トライアルから始めてみてはいかがでしょうか。その一歩が、あなたの会社の未来を大きく変えるきっかけになるはずです。